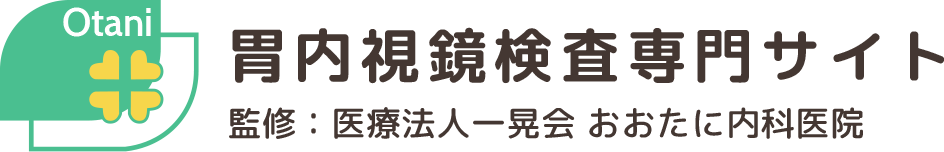ピロリ菌という名前に聞き覚えがある方は多いのではないでしょうか?ピロリ菌は、胃の中でも生きることができる強力な細菌です。正式名称は「ヘリコバクター・ピロリ菌」と言い、愛嬌のある名前の反面、さまざまな疾患を引き起こす可能性を秘めています。
今回は、そんなピロリ菌感染によって起こる胃腸の病気について紹介していきます。また、検査の方法や除菌治療についても併せて解説しますので、ぜひご覧ください。
「ピロリ菌」の感染はなぜ起こる?
前提として、ピロリ菌の感染ルートはまだ明確には明らかになっていませんが、感染の傾向から、飲み水などの衛生環境によって感染する可能性があると言われています。現在日本では、約6,000万人がピロリ菌の保菌者であるという見方があります。
団塊世代よりも少し前の世代では約8割が感染していると言われ、原因として水道が十分に整備されていなかった時期の感染拡大が指摘されています。
若い世代になると感染率は2割程度と言われていますが、幼少期に家庭内感染しているケースも多くあり、そのほとんどは大人になってから検査を受けて発覚します。
幼児期の感染経路としては、虫歯と同じように同じ箸や食べ物の口移しなどが考えられます。
ピロリ菌に感染していることのリスク
ピロリ菌に感染していると、胃がんや胃潰瘍といった胃腸疾患になりやすいと言われています。ピロリ菌が胃の中を動き回ることで、胃の粘膜や壁を傷つけてしまったり、胃の壁が酸の攻撃を受けてしまったりすることで、さまざまな疾患リスクが高まります。
具体的には、ピロリ菌が引き起こす病気として以下の内容が挙げられます。
- ・胃炎
- ・胃潰瘍
- ・十二指腸潰瘍
- ・胃がん
- ・胃過形成性ポリープ
- ・機能性ディスペプシア
- ・特発性血小板減少性紫斑病(ITP)
など
ピロリ菌感染によって慢性胃炎が続くと、胃の粘膜が萎縮したり腸上皮化生が起こったりして、結果として胃がんが発生する可能性があります。
3ピロリ菌感染でみられる症状
ピロリ菌は、感染そのもので何らかの症状が出るということはほとんどありません。ピロリ菌感染の多くは、何らかの疾患を発症した際の症状で見つかります。
ピロリ菌感染によって起こる疾患の症状としては、以下のようなものがあります。
胃潰瘍や十二指腸潰瘍になった場合
胃潰瘍、十二指腸潰瘍では、みぞおちあたりに痛みを感じることがあります。特に食後や空腹時に激しい痛みを伴う傾向があり、薬を飲んでも緩和されることはありません。患者様によっては吐血などの症状を伴うこともあります。
胃がんになった場合
胃がんは、初期段階ではほとんど自覚症状がありません。進行すると、腹痛や胃痛、すぐに満腹になる、体重が減る、貧血になるなどの不調が現れます。
ピロリ菌の検査方法
ピロリ菌の検査では、胃カメラを使用する方法とそれ以外の方法があります。
胃カメラを使用する検査には、以下の3種類があります。
迅速ウレアーゼ試験
胃カメラを用いて組織を一部採取し、ピロリ菌が持っている「ウレアーゼ」という酵素の活性を利用して感染の有無を検査します。
鏡検法
胃粘膜の組織に特殊な染色をして、ピロリ菌を胃カメラで直接探します。
培養法
胃の粘膜を採取し、5~7日培養してピロリ菌が確認できるか検査をしていきます。
胃カメラを使用しない検査には、以下の方法があります。
抗体検査
ピロリ菌に対する抗体の有無を調べることで、感染を判断します。
尿素呼気試験
特殊な薬を服用し、服用前後の呼気を集めて診断します。患者様の負担がなく短時間で行えることから、多くのクリニックが採用している方法です。
抗原法
便の採取を行い、ピロリ菌の抗原の有無を調べる方法です。
ピロリ菌の除菌治療
ピロリ菌の治療は、除菌治療が基本となります。3種類の薬を1週間飲むことで、7割~8割の方は除菌が完了します。
治療は、以下の流れで行っていきます。
一次除菌療法
初めは胃酸を抑える薬を1種類、そして抗菌薬を2種類、合計3錠を組み合わせて行います。1日2回、7日間お薬を服用していただき、改めて検査を行います。検査によって除菌が確認できた場合は治療終了、除菌が完了していない場合には、次のステップへ進みます。
二次除菌療法
一次除菌療法と同じ胃酸を抑える薬と抗菌薬の2錠に合わせて、一次除菌療法とは別の抗菌薬1種類、合計3剤を7日間服用します。服用後に再度検査を行い、除菌が確認できた場合は治療終了です。この段階でほとんどの方は除菌が完了しますが、患者様によっては除菌しきれていないこともあります。そういった場合には、自費診療にて3回目の除菌療法を行います。